
食品添加物って食品のどこに、
どんな感じで表示されているのかな?

今回は食品添加物の表示について紹介するよ!
実は中には表示されていない種類もあるんだ。
食品を購入する際に食品添加物が入っているかどうかを確認する方も多いのではないでしょうか。
この記事を読めば、食品添加物の表示場所やルール、表示されていない食品添加物について知ることができます!
安心して食事を楽しめるように、食品添加物についての正しい知識を身につけていきましょう!
食品添加物の基礎知識

最初に食品添加物の基本知識について簡単に紹介します。
食品添加物の定義
食品添加物は食品衛生法 第4条第2項において、次のように定めれています。
”食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。”
食品衛生法 第4条第2項
わかりやすく言うと、味を調整したり、保存性を高めたり、色や香りを付けることを目的に、食品の製造・加工の際に添加される物質のことを食品添加物と言います。
食品添加物の必要性
食品添加物には主に以下のような役割があります。
- 食品の保存性・品質を高める(保存料、酸化防止剤、殺菌剤など)
- 食品の製造・加工の際に必要になる(膨張剤、にがり、乳化剤など)
- 食を豊かにする(着色料、香料、甘味料など)
- 栄養価を補填する(ビタミン類、ミネラルなど)
使用量などの基準
食品添加物は食品安全委員会により安全性を評価され、純度や成分についての規格や、使用できる食品や量の使用基準が設定されています。
日本で流通している食品であれば、国産品・輸入品を問わず全ての食品で上記の基準が適用されます。
食品添加物の基礎知識について詳しく知りたければ下記の記事もおすすめです!

食品添加物は様々な用途で
食生活を支えているんだね!
記載場所と表示ルール

食品に含まれている食品添加物は、表示のどこを見れば分かるのでしょうか?
食品添加物の記載場所と、表示ルールについて解説していきます。
表示しなくても良い食品添加物や、食品に使用されている食品添加物を詳しく知る方法も紹介しています。
記載場所と記載方法
食品に含まれている食品添加物を確認するには、食品表示(一括表示)の枠内にある添加物欄もしくは原材料名欄を見れば分かります。食品添加物の使用されている量が多い順番で記載されています。
表示方法には3つのパターンがあるのでそれぞれの記載例を紹介します。
1. 添加物欄に記載されている場合
| 品名 | 飲料 |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液、果汁、果汁エキス |
| 添加物 | 香料、酸味料、着色料(カラメル)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア) |
2.「原材料名欄」に記載されていてスラッシュ( / )で区切られている場合
| 品名 | 飲料 |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液、果汁、果汁エキス / 香料、酸味料、着色料(カラメル)、 保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア) |
3.「原材料名欄」に記載されていて改行で区切られている場合
| 品名 | 飲料 |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液、果汁、果汁エキス 香料、酸味料、着色料(カラメル)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア) |
食品添加物の表示ルール
食品に含まれている食品添加物は、原則として全て物質名で表示する必要があります。
「重曹」や「ミョウバン」、「V.C」のように、類別名や簡略名などのわかりやすい名称で表示されていることもあります。
| 類別名、簡略名 | 物質名 |
|---|---|
| 重曹 | 炭酸水素ナトリウム |
| ビタミンC、V.C | L-アスコルビン酸ナトリウム |
| ミョウバン | 硫酸アルミニウムカリウム |
上記のルールに当てはまらない、例外的な方法で表示されているものもあるので、以下で詳しく紹介します。
用途名の表示
以下であげた用途の食品添加物については、物質名以外に用途名も記載しなければなりません。
【記載が必要な用途名】
甘味料・着色料・保存料・増粘剤、安定剤、ゲル化剤又、糊料・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤、防ばい剤
例)「甘味料(キシリトール)」、「保存料(安息香酸Na)」など
一括名での表示
複数の食品添加物の組み合わせで効果が発揮するものに関しては、物質名の代わりに一括名で表示することもできます。
【一括表示できるもの】
イーストフード・ガムベース・かんすい・酵素・光沢剤・香料・酸味料・チューインガム軟化剤・調味料・豆腐用凝固剤・苦味料・乳化剤・水素イオン濃度調整剤(pH調整剤)・膨張剤
表示しなくても良い添加物
加工助剤やキャリーオーバー、栄養強化の目的で使用されているものに関しては、食品添加物の表示が義務付けられてはいません。
【加工助剤】
食品の加工の際に使用されるが、最終的に食品に残らない食品添加物
【キャリーオーバー】
原材料の加工に使用されるが、食品自体には使用されず、量が少ないために効果が発揮されない食品添加物
【栄養強化の目的】
ビタミンA、βカロテン等のビタミン類やミネラル類など
食品添加物の詳細が知りたいときは?
表示されていない食品添加物については知りたいときはどうすれば良いのでしょうか?
食品に使用されている食品添加物について詳細に知りたいときは、容器や包装の一括表示の枠内に記載してある、食品関連事業者(表示責任者)に問合せをすれば答えてくれます。
もし上記で紹介した内容(「類別名や簡略名、一括名などの詳細」や「表示されていない食品添加物」)などについて詳しく知りたくなったときは、実際に問い合わせて確認してみましょう!

表示されていない食品添加物も
ちゃんと確認できる方法があるんだね!
添加物の不使用表示について

お店などで買い物をしていると、「着色料無添加」や「保存料不使用」と表示されている食品を見かけることがあるかもしれません。
令和4年3月に消費者庁から上記のような添加物の不使用表示についてのガイドラインが制定されました。
添加物の不使用表示についての規定がなく、消費者が食品を選ぶ際に混乱を招く可能性があるため、このガイドラインが制定されたそうです。
添加物不使用製品を選ぶときのポイントにもなるので、制定されたガイドラインについていくつか抜粋して紹介して行きます。
無添加の表示について
今までは単に「無添加」という表示ができましたが、ガイドライン制定後は「着色料無添加」や「保存料不使用」など、何の成分が無添加・不使用なのかが明確に表示されるようになります。
また同じような機能を持つ食品添加物を使用している場合は、無添加の表示ができないようになります。
例)保存効果を目的に「酸化防止剤」を使用している食品に「保存料無添加」と表示することはできません。
「人工」と「合成」の用語について
今までは「人工着色料無添加」や「合成化学調味料不使用」などの表示ができていましたが、今後はこういった表示がなくなります。
食品表示基準において、食品添加物は化学的合成品と天然物の区別をせずに表示する必要があり、「人工」や「合成」「化学」「天然」といった表示をすることは不適切だと判断されたようです。
健康や安全、美味しさとの関連
食品添加物は国により安全性が評価され、使用されています。そのため、「保存料不使用だから安全」などの健康や安全に関連させて表示するすることはできません。
また「着色料不使用だから美味しい」のように、合理的な説明がない状態で、食品添加物を使用していないことが、食品の美味しさと関係があるという内容の表示をすることはできません。

食品添加物が気になる人にとっては
表示がわかりやすくって嬉しいね!
食品添加物の表示方法についてのまとめ
今回の記事では、食品添加物の表示場所やルール、表示されていない食品添加物ついて紹介しました!
それでは今回のポイントをおさらいしましょう!
- 食品添加物のおかげで保存性が高まったり、食が豊かになる
- 使用されている「食品添加物」は食品表示(一括表示)に記載されている
- 一括名で表示されたり、表示しなくても良い食品添加物もある
- 添加物の不使用表示について制定されたガイドラインがある

食品添加物について気になる方は、
食品の表示を良くみてみよう!

毎日の食事を安心なものにする為にも、
食品添加物の正しい知識を身につけよう!
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!
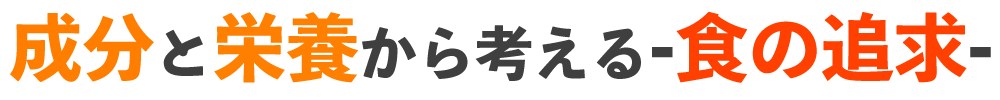



コメント