
最近地震や大雨が多くて怖いね。
事前に何か準備できることはあるのかな?

今回は大きな災害が起きたときに備えて、
非常食の選び方や必要な量を紹介するよ!
非常食ってどんなもの?
近年、大雨や地震などの自然災害が増えてきているように感じます。
もし大きな災害が起きた時に、食べ物や飲み物が準備できてなかったら困ってしまいますよね。
今回の記事では、災害に備えた非常食の管理方法や必要な量について解説しています。
非常食を準備するときに選ぶ3つのポイントも合わせて紹介していますので、よかったら読んでみてください!

非常食の必要性
大雨や地震などの災害は、いつどこで起こるのか誰にも予測することはできません。被害の状況によっては電気・ガス・水道が止まったり、物流の混乱などにより食料を手に入れることが困難になってしまう事も考えられます。
そんな非常事態に備えて、事前に食料や飲料を備蓄したものを「非常食」と言います。
国だけでなく県や市町村などの自治体は災害に備えて「非常食」の備蓄を行っているそうですが、道路の破損や洪水などで家単位で孤立してしまう可能性も考えられます。
そういった状況に対応するためにも各家庭で非常食を備蓄する「家庭備蓄」という考え方が重要になってくるのです。
非常食の種類
それではどんな食べ物を「非常食」として備蓄しておけばいいのでしょうか?
いくつか例を挙げながら紹介して行きます!
飲料水

人は水分を取らないと数日で命を落とすと言われています。
飲料としてだけではなく、調理などにも使えるので飲料水は必ず備蓄しておく必要があります。
米やパン(主食)

人が動いたりするのに必要なエネルギー源となる、炭水化物を含む米やパンなどの主食も備蓄が必要です。
「アルファ化米」というお湯や水を入れるだけで食べれるお米や、缶詰入りのパンなどがお勧めです。
缶詰やレトルト食品(主菜)

肉や魚などの加工食品は、身体をつくるたんぱく質を多く含み、食事のメインとなるおかず(主菜)になります。
缶詰やレトルト食品などの調理が不要でそのまま食べられるもので、長期保存可能なものがおすすめです。
野菜ジュースやサプリメント(副菜)

災害が起きて非常食だけを食べる生活が続けば、栄養のバランスも偏ってしまいます。
野菜の代わりに手軽に栄養補給ができる、野菜ジュースや栄養サプリメントを備蓄することもおすすめです。ビタミンやミネラルなどの必要な栄養素を補うことができます。
お菓子

長期の避難生活などが必要になってしまった場合を考えて、お菓子を備蓄することもいいかもしれません。
甘いお菓子は手軽なエネルギー補給としてだけでなく、避難生活のストレスを低減してくれる効果も期待できます。子供がいる家庭は特におすすめです!
食品以外であると便利なもの

食品以外でも、調理に役立つものも合わせて備蓄しておくことも大事になってきます。電気やガスが止まってしまったら、調理どころかお湯を沸かすことも難しくなってしまします。
そんな状況に備えてカセットコンロを準備しておくと、暖かい食事が取れて良いかもしれません。冬場は特に温かい食事が心身ともに大事になってくることでしょう。

備蓄したほうがいいものって結構あるんだね。
でも非常時のことを考えたらどれも必要そうだね!
非常食の量と管理方法

非常食として備蓄すべき食品を紹介しましたが、それぞれどれくらいの量を準備すれば良いのでしょうか?
ここからは何日分の食料を備蓄すればいいのか、また非常食をどうやって管理していけばいいのかについて紹介して行きます!
非常食は何日分必要?
災害時を想定して非常食を備蓄すると言っても、具体的に何日分ぐらい準備しておくのがいいか基準がよくわからないですよね。
農林水産省のHPでは備蓄する量を以下のように紹介しています。
自宅での避難生活を想定して、最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄が必要といわれています。
引用:農林水産省「特集1 非常食(2)」
栄養のバランスを考えながら、最低でも3日分の非常食(食料、飲料水、カセットコンロ等)を準備する必要があるみたいですね。
災害が起きた当日は、情報収集や安全の確保などが必要になるため調理しなくても食べることが可能な缶詰やレトルト食品、栄養補助食品などを1日分は準備することが望ましいです。
飲料水に関しては、1人あたり1日1リットルの水が必要になります。調理にも使うことを想定する場合は1日3リットルの水を備蓄することが必要になります。
おすすめの管理方法!
最低でも3日分の食料を備蓄した上、賞味期限などを気にしながら保管していくのはとても大変なことだと思います。
最近は、日常から使用している食品を災害時にも非常食として使用する「ローリングストック」という管理方法の考え方があります。

「ローリングストック」とは、普段食べている食品を少し多めに買い足しておき、賞味期限の古いものから食べて消費していきます。そして消費して減った分の食品を追加で買い足すことで、常に一定の食料が家に備蓄されている状態を保つという方法です。
この方法を行うことで賞味期限切れを起こすことをなくしたり、非常食を置くスペースを節約できるメリットがあります!
「ローリングストック」と合わせて、非常用袋やリュックなどに持ち出す用の「非常食」も備蓄しておくと避難しなければならなくなった時に安心です。
非常食を選ぶ時の3つのポイント!

最後に非常食を選んで買うときの3つのポイントについて紹介します。
自分の好みや食生活に合わせて、必要な食品を備蓄して行きましょう!
電気・ガス・水道が止まっても食べられるもの
災害の発生直後などは特に、電気・ガス・水道などのライフラインが止まってしまう可能性があります。そんな非常事態でも調理や加熱が不必要な非常食を準備しておきましょう!
缶詰やレトルト食品、パンなどがあると便利です。レトルト食品の中には加熱やお湯がなくても、発熱剤というものを使って温かい食品が食べれるものもあります。
美味しさや栄養バランス
災害などが起こり非常事態になると、気が休まる事のない日々が続くことになります。そんな生活で「食事」は楽しみの一つになり、心の安定やストレスの低減にもつながります。
非常食を選ぶ際には自分の好きな食品であったり、可能であれば実際に試食してみて美味しいと感じるものを選ぶようにしましょう!
また非常食を食べ続ける生活が続くと、食事の栄養バランスも偏ってしまうこともあるそうです。炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルなど必要な栄養素が取れるように考えて非常食を選ぶようにしましょう。
野菜ジュースやサプリメントを用いて、不足する栄養素を補うこともおすすめです。
バリエーションを豊かにしよう!
非常食を準備する際には同じ食品をたくさん揃えるよりも、味や食感の違ういろんなジャンルの食品を準備することが望ましいです。
先ほど説明した通り非常事態の生活が続くと、「食事」は楽しみの一つになります。同じメニューの食事が続くと飽きて楽しむことも難しくなってしまうので、可能であれば食事のバリエーションを増やして楽しめるようにしましょう。
お菓子などの甘いものを一緒に備蓄しておくと、同じような食生活にもメリハリが出てくるのでおすすめです。
非常食についてのまとめ!
今回の記事では、災害に備えた非常食の管理方法や必要な量について紹介しました!
それでは今回のポイントをおさらいしましょう!
- 災害などの非常事態に備えて「非常食」を備蓄する必要がある
- 水、主食、主菜、副菜などをバランスよく備蓄することが大事!
- 最低でも3日、できれば1週間分の備蓄が望ましい
- 日常の食品を災害時に非常食として使用する「ローリングストック」という考え方がある
- 美味しさやバリエーションなど食を楽しむための工夫も大事!

必要な栄養素を摂るだけでなく、
非常時でも食事を楽しめるような工夫が大事だね!

いざという時に慌てないように、
日頃からしっかり準備をしておこう!
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!
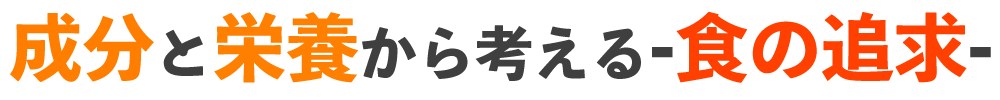



コメント